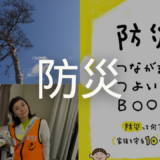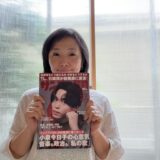2024年6月4〜7日
能登町にて災害復興活動を行う『災害支援JOCA能登チーム』にボランティアとして参加してきました。
詳しいことはnoteに9回シリーズで書いています。
続きを読む: 防災)能登災害ボランティア体験


私が訪れた場所は、能登町にある復興支援ボランティア拠点です。一軒の古民家で20人ほどのボランティアが寝泊まりできるスペースがあり、自炊が可能です。台所、トイレ、寝袋などの寝具が備わっており、電気水道も通じているため普通に生活することができます。
情報を集約する事務局スペースを設け、そこで毎朝集まってミーティングをしてチームに分かれ、支援場所に赴き活動をします。
自給自足自立が基本の災害ボランティア活動において、寝る場所、食べる場所、トイレと風呂の確保はとても心強いことです。
10日間くらい滞在するボランティアが入れ替わり立ち替わり、役割を担っていくので、引き継ぎも大切です。(ボランティアマネジメントは丁寧ですが、作業伝達コストを考えると長く滞在できる方が良いと思います)
行政や他団体と情報の共有や報告をする事務局スタッフやボランティアをマネージメントする人の存在も重要です。
夜は地元の就労支援施設・レストラン日本海クラブからの提供のお弁当が届けられますので、活動から帰ってきたら調理済みのご飯があるので幸せです。
「安心してボランティアできる場所だよって伝えてもらいたい」と、コーディネーターのシミさんが言っていました。ボランティアのやりがい・安心感・充実感も感じられる温かみのある拠点です。



復興支援JOCA能登町チームでは、他の団体と連携しながら仮設の見守り活動の一環で、集会所などで健康のための体操やレコード鑑賞、JOCAカフェ(お茶会)などのレクリエーションを実施しています。
参加を呼びかけることをきっかけに会話が発生したり、何気ないやりとりからその人の健康状況や困り事を察知していきます。
お茶会や、音楽や、お話し、体操など、いろんなテーマを繰り出して、外に出るきっかけにしてもらいます。
仮設入居の開始は被災地にとって新たなフェーズであり、そこでむかえる引越しは支援者が入居者と出会える貴重な機会です。そのタイミングで少しでも顔の見える関係性を作っておくことがその後のつながり作りに役立っていくと感じました。



復興支援JOCA能登町チームの活動は「支援が必要な人や場所に、適切な支援が届くこと」をモットーとしています。
この活動の軸がブレないようにすることが肝心なのだなと短いボランティアの間に感じました。
ボランティアにできることは限られている。でも、災害復興のニーズは多様で広範囲です
自分たちのミッションに立ち戻って考えることが大切でしょう
「1人でも孤独な状況の人を減らす。そのために、情報、ヒト、モノ、なごむ場の提供などありとあらゆることをする」と語るプロジェクトマネージャーで看護師の山中さん。
ほんとうに必要な支援は人によって様々です。
被災された人が前に進む力はバラバラです。それぞれのペースで進んでいます。
全員に等しくなされる支援とは別に、個別の支援も必要になってきます。
「孤独死を出さない」という強い思いをもち、目的を持って穏やかにヒアリングをすることが、もともと存在していた要支援者を浮かび上がらせることになります。それは被災地だけではなく、日本の各地地域でも必要な活動なのだとも感じました。



私が訪れた6月初旬の段階においてはいくつかの避難所が開設中。同時に仮設住宅への入居も進んでいました。道路に地割れが残るところも多くあり、公費解体がようやく始まったというくらいで倒壊状態の家屋の多くが残っていました。
仮設住宅への入居に合わせて、壊れた自宅から家財道具を取り出したり、新たな住居へのガス水道電気の契約をしたりという引っ越し作業も行われることになります
復興に向けた状況は変わり続けています



能登町内を見てみると、田んぼには水が張られ田植えがなされています。海は青く、イカなどの海産物が豊富。みどり豊かな自然環境。半島の内海に面しており、海の向こうに立山が見えるのが荘厳でかっこいいのだと聞きました。漁港の一角で地域の人の憩いの場になっている美容院、全壊した居酒屋を再建したいと語る女性、地域素材や地元の生乳を100%使ったジェラートを提供する販売店、迫力ある伝統の祭り「あばれ祭り」が楽しみだと語る男性、壊れてしまった自宅に寝泊まりし、沢の水を使い畑の玉ねぎの味噌汁を作り、元気に暮らしていると笑う高齢男性とも出会いました、
能登の皆さんはしっかりと地に足をつけて生活していこうとしているのだと感じました。
未来の災害を予知することは難しいです。私たちにできることは過去から学ぶことだけです。これまでの災害経験から未来の被害を減らしたり、復興の速度を早めていくことはできます。
能登の復興に携わることが、未来の私たち全員の災害被害を減らすことになると信じています。